About OSMOS
OSMOS(オスモス)は、構造物のモニタリングに光ファイバを用いたセンシング技術です。
OSMOSセンシング技術で、安心・安全な持続可能社会の構築に貢献します。
我が国では、橋梁やトンネルをはじめとする社会インフラ構造物や発電所・エネルギープラントなどの生活を支える施設・設備の老朽化問題に直面しています。
また、近年の気候変動等の影響により頻発化・激甚化している自然災害による被害を如何に軽減できるかが社会課題となっています。
OSMOS構造ヘルスモニタリングは、これらの社会問題に対して、生活の基盤となる構造物や設備の監視・保全・運用を高度化・効率化するためのソリューションをご提案致します。
OSMOS(オスモス) とは、 Optical Strand Monitoring System の略語で、光ファイバを用いた光学ストランドセンサにより構造物の挙動をマイクロオーダーで検知します。
構造物の変状を検知するため、OSMOS システムでは種々のセンサを準備しています。代表的な光学ストランドセンサは、光ファイバをセンサに用いており1m固定間の変位を高精度で計測します。


構造物の変状を把握するための種々の特性を監視
 変位
変位 き裂
き裂 傾斜
傾斜 振動 / 衝撃
振動 / 衝撃 温度
温度
Service Flow
OSMOS構造ヘルスモニタリングのサービスフロー
-
1
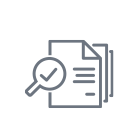
モニタリングシステムの検討・選定
お客様のニーズに対して、モニタリングの実現可能性の検討を行い合理的な手法をご提案します
-
2

準備と計画
システム計器の手配 (*1) と現場設置工事を計画します
-
3

システムの設置
センサシステムの設置工事から定期的なメンテナンスまでトータルでサポートします
-
4

監視と計測
構造物の挙動を常時監視し、データを収集します
-
5
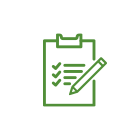
計測データの記録
計測データはインターネット通信を介して安全な専用クラウドサーバーに保存されます (*2)
-
6

分析と評価
収集したデータの分析を行い、構造物の評価結果をご報告します
(*1)センサ機器の在庫がある場合は、即時に対応可能です。国内に在庫がない場合、フランスに発注するため輸送に 1 か月程度の期間が必要となります。
(*2)クラウドに保存されたデータは、 Web アプリ SafeWorks によって随時お客様でもモニタリング状況をご確認いただけます。
What’s new新着情報
お電話でのお問い合わせ
045-307-4744受付時間帯 10:00~17:00

